(零)
雨が降る。
ネオンとアスファルトと人にまみれた街に。
黒い夜の雨が。
冷たい雨が。
墜ちて、叩いて、流れて。
その帷(とばり)の中を、黒髪の少女は歩き続ける。
傘も差さず、
すっかり濡れてしまった不似合いな寝間着から白い肌が透けて見える。

裸足の足が水たまりで小さな音を立てる。
黒髪の少女は歩く。
すれ違う人々の奇異の視線も。
背中にかけられる問いかけも。
助けようと差し伸べられる手も。
何もかも振り捨てて、
ただ、歩き続ける。
その姿は、惨めで、哀れで、痛ましくて、そして―――まるで幽玄の国の姫君のように―――美しかった。
通行人の中には、黒髪の少女の身を按じて最寄りの交番に連絡するものもあったが、しかし、誰が駆けつけても、探し回ってもその姿を捉えることは決してなかった。
黒髪の少女は何処に?
人々は不審に思いつつも、最後にはこう納得する。
きっと、他の誰かが保護したか、さもなくば何かの見間違いだったのだろう……と。
黒髪の少女が無意識に穏行の技を使い、その気配を断ったのだとは知るはずもない。
その身体を容赦なく叩き続ける雨も。
肌にまとわりつく濡れた髪と服の不快感も。
芯にじわじわとしみ込んでくるような寒さも。
何ももたらしはしない。
黒髪の少女には何もなかった。
取り巻く世界にも、内なる世界にも。
何もなかった。
あるのはただ空と虚。
黒髪の少女はふと足を止め、天を仰ぐ。
分身である月を探し求めるかのように。
沖天に見えるのは、ただ真っ暗の空。
何処を探そうと輝きなど見あたらない。
黒髪の少女と同じ、夜闇の色だ。
途方に暮れたかのように、黒髪の少女は再び歩き出す。
空の闇よりなお深い、漆黒の瞳のまま。
少女の瞳は、何一つ映し出すことのない闇の鏡。
その奥の奥の奥に映るものはただ一つ。
紅茶色の髪の少女。
(壱)
雨は尚も降り続ける。
人気のない夜の児童公園。
塗装の剥げかけた遊具、華のない花壇、
落書きにまみれた看板、誰かが蹴り倒してでも行ったのか、屑籠が横倒しになっている。
何処か墓場めいて見える。
弱々しく点滅を繰り返す切れかけた誘蛾灯が照らし出すのは、ブランコに乗った人影。
千華音の無惨な姿であった。
その瞳は何ものも映さず。
その耳はどんな音も捉えず。
その肌は何も感じず。
その心は乾き、ひび割れ、半ば砕け散っていた。
そんな壊れかけた心の片隅で、ぼんやりと思う。
いつ、どうして、何故ここに来たのか?
違う。そんなことではない。
千華音自身も理由など判らないし、たとえその自我が戻ってきたところで、知りたいとも思わないだろう。
意味など無いのだ。
今、思うのはただ一つ。
空洞と化した千華音の中を吹き抜けてくるもの。
風の唸り?
遠雷の轟き?
それとも唄?
それは千華音自身の、その心の深淵から湧き出してくる。
ぞっとするほど虚しく、おぞましいほどに冷め切ったそれ。
心が穿たれ、貫かれて、
その疵痕から、じくじくと噴き出してくる。
不吉な呪歌のように。
禍々しい妖風のように。
激しくも、鋭くもないそれは。
『棘』の叱咤よりも苦々しく。
『影』の嘲弄よりも容赦無く。
千華音自身を責め苛み、浸食し、穿ち、突き崩していく。
もろもろと砕け崩れていく欠片と共に溢れ出してくるのは。
ただ一つの言葉。
「何故?」
「何故?」
「何故?」
「何故?」
そう―――
何故なのだろう?
繰り返される問いが。
心の残骸を吹き抜け、その名残を風車のようにくるくると廻らせる。
動いても動いても、進みも、戻りもしない。
ただからからと廻るだけの無意味な繰り返し。
それでも千華音は繰り返さずにはいられない。
ただ一つのことを。
どうしてあんなことを?
どうして?
―――と。
(弐)
媛子の部屋、その薄闇の中で。
千華音は媛子と対峙していた。
息苦しくなるほどの静寂の中、千華音の心は激しく荒れ狂う。
熱と混乱の燃えさかる火の嵐。
―――違う。違うの。
千華音の魂が、声にならない叫びを上げる。
何が、違うというのだろう?
のど元に突き付けた刃の殺意の煌めきと。
見つめる瞳に映る魂の輝きと。
どちらなのだろう?
いや、そんなことは決まっている。
コソコソと音もなく。まるで殺し屋のように―――そうではない。もっと惨めなものだ。―――盗人のように、媛子に迫ったことが。
ただ、恥ずかしくて。情けなくて。
そして―――。
【本当にどうしようもない……莫迦ね】
『棘』がここにいるなら、そう言うだろう。
【殺すと決まっている筈の相手に。
あなたが楽しんでいる『お付き合い』とか言うママゴトと何処が違うというの?】
【冗談めかして嗤えばいいのよ。夜のせいにでもしてしまいなさい。パジャマパーティとか言うのでしょう?】
【それが、作法ってもの……そうなのでしょう?】
そう言って、嘲笑うだろう。
違う―――。
『お付き合い』などではなかった。
作法などではなかった。
たとえ無我の中での行為ではあっても。
そこには、そこに至るまでには嘘はない筈なのだ。
駆け引きという名の嘘で繕っていい筈もない。それは、混じりけのない本意なのだ。
だから―――。
千華音にとって永劫にも等しい瞬間がすぎていく。
その間も千華音の瞳は、媛子の姿をとらえて放さない。
背けることも、閉じることも、出来はしない。
何を言えばいい?
何をすればいい?
何処かに正解は有るのか?
十五年間積み重ねてきた、『御神娘』としての生。
ただ闘うためだけに築き上げて来た時間。
どれほど遠くても、険しくとも、そこには必ず正解に至る道があった。
でも今は―――。
千華音には何も判らない。
ただ一つ、判っているのは、このままではいけない―――ただそれだけで有ることを、
理性でも知性でもない別の何かで悟っていたた。
けれど―――。
媛子の唇が、震えるように呟く。
その瞳が潤んでいるのが判る。
媛子は良く泣く娘だ。
また迷惑をかけたと言ってはしょげかえり。
映画に感動したと言っては泣き。
人目もはばからずに、良く涙を流していた。
始めはその『御神娘』らしからぬ心の脆さに呆れ、いつの間にかその真っ直ぐな素直さが愛おしく思うようになって行ったのだ。
でも―――。
この涙は違う。
今までとは違う。
浮かべるものでも、流すものでもなく。
溢れ出してくるものだから。
胸が痛む。
切り刻まれるように。引き裂かれるように、灼き焦がされるように。強く、強く。強く。
まるで我がことの―――いやそれ以上に。
当たり前のことだ。
これは……。
媛子の痛みなのだから。
媛子の
早く。
早く。
止めてあげないと。
止めてあげないないといけないのに。
媛子を―――。
唇も、身体も、もどかしいほど動かないのに。
激しい後悔と焦燥感だけが、何も紡がぬ糸車のように虚しい音を立てて回り続ける。
その時―――。
媛子の手が動いて。
千華音の身体を突き飛ばす。
子供のような、あまりにも非力なその掌に。
込められたのは、
明確な拒絶。
その衝撃と、驚愕と、絶望の中で。
千華音の心は、微塵に砕け、
深い深い……何処までも深い底なしの、
地獄の最下層よりもなお昏い、
闇に墜ちた―――。
(三)
そして、気付いたら、ここにいた。
何も観ず。何も聞かず、何も触れず。
全ては夢の中の出来事のように、霧の中の何かのように、霞み、薄れ、まるで海の向こうの異国の出来事のように―――ただ何処までも遠く感じながら。
千華音は砕けた心の片隅で思う。
バラバラ。
何もかも。
無と空と虚と渇と痛とが酷く散らかったまま、何一つ纏まってくれない。
酷いものね。
なお降り止む気配を見せぬ雨たちが千華音を打ち続ける。
これは天の……『大蛇神』の罰なのだろうか?
『御神娘』に似つかわしくない千華音をに怒っているのだろうか?
しかしわき上がってくるのは、悔恨でもなく、自傷心でもなく。ただ空だ。
おかしいわね。
と千華音の欠片が考える。
身体はこんなにも濡れているのに。
何故こんなに乾いていると思うのだろう?
猛暑の砂浜に打ち上げられた、干からびた海綿の死骸ように、カサカサに乾ききって、何一つ吸い込もうとはしない。
もういい。
このまま千華音自身も、この降りしきる流れの中で、熔けて流れて……。
消えてしまえばいいのに。
そうなってしまうのが、今の千華音には、いっそ相応しいと思う。
だから……。
その時。
千華音は複数の気配を覚える。
雨音に混じって。
何者かの……違う。
鍛え上げた千華音の闘争本能は状況を瞬時に理解する。
右の植え込みに二人。
後ろの梢の上に一人。
左の四阿(あずまや)の柱の陰に二人。
正面、ゾウの滑り台の裏に一人。
総勢六人。言うまでもなく『九蛇卵』だ。
おそらくは日之宮の『九蛇卵』だ。
媛子は頼み込んで押さえていると言ったけれど、跳ね返りものは必ず出てくる。
あの夜の皇月の家の二人のように。
いや、更に遠巻きに十数人単位での包囲網がしかれている。
達者なものね。と千華音は思う。
見事に殺気や闘気を押し殺している。
警戒心の強い野生動物ですら、その接近に気付くことはないだろう。
しかし、惜しいかな『消そう』という意識があまりにも強すぎる。
これでは意味がない。
ことさらに意識する必要もなく、ただの空となり、無となる。
それが『穏行』なのだ。
千華音自身が、何度もそう叱られ、傷付き、苦しみながら鍛錬を繰り返した。
四阿に潜む一人が、僅かに足の位置を変える。
駄目よ。
そこからじゃ角度が悪い。
距離も遠すぎる。
『鏢』か? 『針』か? それとももっと他のものか。
何であっても、それではまず万が一にも当たらない。
回避すのも、捌くのも、防ぐのも、自由自在だ。
たとえ当たったところで、皇月千華音を『行動不能』にすることなど、出来はしないのに。
などと、他人事のように批評をしつつ千華音はぼんやりと待ち続ける。
何を?
何でもいい。その瞬間を。だ。
こんな無惨な時間を終わらせてくれるかも知れない、その瞬間を。
降りしきる雨粒の一つが千華音の右眼を叩く。
世界の半ば塞がれ、歪む。
その刹那―――。
『九蛇卵』たちが、一斉に雨の中を跳んだ。
音もなく千華音に殺到する。
そして―――。
(四)
千華音は再び街を彷徨っていた。
その身体には傷とも言えぬ傷、寝間着の一部が僅かに裂かれた跡が有るばかりだ。
しかし、千華音は何一つはっきりと覚えてはいない。
ただぼんやりと思うだけだ。
闘ってしまったのね……きっと。
右に跳び、左に走り、舞うように、踊るように。
『九蛇卵』の群れを突破して来たのだ。
千華音の心とは関係なく、身体は勝手に動く。
『九蛇卵』の何人かは、何処かを砕かれ、倒れ伏していることだろう。
今頃は仲間が回収しているはずだ。
杜束島の秘密を守るためにも、証拠は残せない。
気力が枯れ果てても、心が微塵に砕けても、身体はこんなにも自在に動くのだから。
自分はやはり『御神娘』なのだ。
闘って、闘って、ただ『大蛇神』の御為(おんため)に尽くすのだ。
それより―――。
敵の攻撃を受け流すための、闘技の一環とはいえ、
せっかく媛子が貸してくれた寝間着が。
千華音の砕けた心が微かに痛む。
どうして今更そんなことが気になるのか。
切れてしまった夢の糸の名残をいつまでも惜しんでいるかのように。
なんて不様な……。
何も考えたくない。
何処にもいたくない。
今すぐに跡形もなく消えて無くなってしまいたい。
こんな自分は……。
その前にスッと影が差す。
十数人の皇月の『九蛇卵』。
そしてその背後には。
優雅に嗤う影が一つ。
近江和双磨だ。
「ごきげんよう。皇月の御神娘」
そう言って、影は裂けるように妖しく、微笑んだ。
(五)
千華音は自分の部屋に戻っていた。
その身には、媛子の部屋に残してきたはずの制服を纏(まと)っている。
その目の前にはこれも残してきた太刀と携帯電話が、置かれていた。
きっと『九蛇卵』と双磨の仕業だろう。
続けろ……ということね。
当然だ。
それが御神娘の使命であり、宿命であり、運命なのだから。
千華音はぼんやりと窓の外の空を空を仰ぐ。
文字通り、抜けるような青空だ。
雲の切れ端が、空を流れていく。
随分と空が高い―――。
もう夏も終わる。
秋が来る。
熱くて、激しくて、濃密で。
何もかもが熱を持って、忙しなく動いていて。
そのくせ、時が止まって感じるような。
そこには、決して終わらない何かがある。
そう錯覚するほどに、眩く、華やかに煌めいていた二人の時間はこれで終わるのだ。
そんなはずはないのに。
時は決して止まることはない。
等しく動き続ける。
そして必ず来てしまう。
御神娘の十六歳の誕生日。
『御霊鎮めの儀』の日はもうそこまで来ているのだ。
ほんの余興、運命の日までの暇潰し。
駄菓子のように軽くて、口当たりのいい―――日溜まりの子猫たちのような―――じゃれあい。
作戦で、計算で、予定調和な。
文字通りの『お付き合い』。
始めはただそれだけでしか無かった日々。
これでも、もう―――還れない。
百も承知の筈だった事実が、絡みつく荊の如く千華音の心を締め上げる。
幾百、幾千、幾万の、無数の思い出が食い込んでくる。
それは苦く、鋭く、それでいて何処か心地いいもので。
万華鏡のように、華やかに舞う毒針たち。
そして―――。
その時、携帯の呼び出し音が鳴り、千華音を怠惰な思索と連想の苑から引き戻す。
皇月の『九蛇卵』でもなく。
バイト先からの連絡でもなく。
それは特別な、媛子専用の呼び出し曲。
ただの連絡用の道具と思っていた千華音に、特別な意味を教えてくれた曲。
いつだったか媛子が好きだと言っていた、曲。
「!?」
千華音が反射的に携帯を手に取る。
媛子からのメールだ。
それはタイトルも本文もない。
砂原のような真っ白な空のメール。
会いたい。
会いたい!
会いたい!!
媛子。
弾かれたように千華音が立ち上がる。
しかし、その足は、そのまま歩みを止めてしまう。
会って、どうすればいいの?
何を言えばいいの?
あの夜のことを。
あの、秘め事を―――。
一体、何を言えばいい?
何を?
千華音が縋るように、携帯の画面に視線を落とす。

そこには何もない。
ただ無情なまでになにもない―――白。
「……」
千華音の指先がゆっくりと動き、電源の電源を切る。
今までは媛子から何度も、何度も、何度も連絡をもらっていた。
千華音側から連絡を取ったことなど只の一度もなかった。
だんだん媛子の存在を好ましく思うようになってからでも。
恐らくそうして無為に連絡を待っている時間さえも、気に入ってしまったから。
化石のように固まった時間の中で、千華音は己の想いを確かめる。
自分は媛子を好き。
紅茶色の髪。
紫水晶色の瞳。
桜色の爪。
好き。
薄くて、形の良い胸。
チェリーのような唇。
西洋人形を想わせる華奢な手足。
本当に好き。
何処か幼い、粉砂糖のように甘い声。
真摯な眼差し。
その小春日和の温もり。
モジモジして、おどおどして、ちょっとしたことですぐ涙ぐんでしまうような気弱さ。
そのくせ笑うと、華が咲いたようで。
鮮やかにくるくると変化するさまが。
幼い頃に除いた万華鏡のようで。
何もかもが。
何より愛おしい。
愛している。
誰よりも愛している。
それはこの世のどんなものより、『御神娘』の使命よりも重い。
友達でも、家族でもなく、少女を少女として愛している。
抱き合って。
キスをしあって。
お互いを熱く確かめ合って。
そして―――。
やっと判った。
媛子の言っていた言葉の意味が。
『一番大切な人』。
今、確かに千華音の中には存在するのだ。
日之宮媛子が好き。
愛している。
あの日の午後のローカル線で感じたことは、より確かな形と眩しい輝きを伴って、千華音の中に刻まれている。
自分自身より、他のどんなものより、ずっとずっと大切で
ふとその人を思うだけで、振り回され、かき乱され、自分が自分でいられなくなる。
それが―――。
どうしようもなく心地いい。
知らなかった。
こんなにも、素敵なものだったなんて。
日之宮媛子。
心の中で繰り返し唱えるだけでどんどん幸せになれるお呪(まじな)い。
皇月千華音の『一番大切な人』。
でも―――。
でも……と千華音は思う。
媛子はどう思っているのだろう?
双磨は嗤った。千華音の感情は砂糖菓子のママゴトだと。
媛子も、そう思っているのか?
千華音に向けてくれた好意は、『一番大切な人』の意味は、千華音のそれとはまったく違うものなのか?
あの時、媛子は言った。
クラスのみんなかが普通にしていることだから。
そう言うことなのか?
女の子たちが一緒に盛り上がるためのツールなのか。
大事なお友達。
違う。
そうじゃない。
たとえそのために全てを捧げられてたとしても。
恋人と友達の間には、どうしようもなく深い亀裂が穿たれている。
果たしてそれは良いことなのだろうか?
どちらかが、劣っているもの。歪んでいるもの。悪しきものなのだろうか?
千華音には判らない。
そもそも友達などいないのだから、比べようもないのだ。
それに、、無理矢理に決めつけてどうにかなるものでもないのだろう。
ただ、違う―――たとえどれほど似通って見えたとしても―――千華音にとっては、きっと違うものだ。
ただ、媛子にとって千華音が、誰よりも大切な友達だとすれば。
少女が少女を愛することは、受け入れられないのことなのか?
千華音は身勝手な行為で、媛子の気持ちを裏切ったことになるのか?
だとすればとうてい許されることではない……絶対に許されない。
苦しい。
この手で自分を引き裂いてやりたいほどの、激情と激痛が心に突き刺さる。
無理だ。
千華音は強く思う。
それは巌の如き確信であり、鋼の如き信念であり、揺るぎなき大地である。
もう自分に媛子は殺せない。
『杜束島』の未来の為であっても。
『大蛇神様』の為であっても。
『御神娘』の使命の為であっても。
たとえ、その罰の代償が自分の命であろうと。
できない。
これほどまでに愛おしく思える相手を手に懸けるなんて。
絶対にできない。
だから―――。
あの約束は無しだ。
媛子を出来る限り傷付けないように。
終わらせたい。
その前に―――。
たとえどんな結末になっても、この想いを伝えたい。
媛子……私はあなたが好き。
あなたを愛していると。
そして、媛子の気持ちを、確かめたいと。
千華音の心は決まった。
たとえそれが到達点などではなく、更なる逡巡と迷いの迷宮への入り口でしかなかったとしても。
(六)
朝。
千華音は季節と関わりなく、―――任務がない限りは―――ほぼ日の出と共に目覚める。
それが十五年間身体に刻み込んだ、千華音のバイオリズムだ。
今朝も雲一つ無くからりと晴れている。
吹く風も心地いい。
このところずっとそうだ。
それから、短い瞑想と身体をほぐす柔軟体操。
朝の掃除。から拭きと箒。
塵一つ無い部屋は、千華音の好きなモノの一つだ。
それからシャワーで汗と雑念を丹念に洗い流す。
その後は朝食だ。
海草サラダとミルクとエッグトースト、日によっては果物を少し。
食後には媛子に教わったアロマを炊く。
カモミールとバニラ。
芳香が気分を落ち着かせる。
料理も、知識も、ファッションセンスも千華音の方が遙かに上だけれども、こればかりは、媛子の炊いたものにはかなわない。
最後にメイク、リップも、あくまで軽めに。
流行を強く意識せずに、派手すぎては媛子を気後れさせてしまうから。
それから登校だ。
電車を乗り継いで、きっちり時間通りに着く。
通学路を歩く。
速すぎず、遅すぎず。
特に意識はしていないはずなのに、いつの間にか媛子の歩幅に合わせている。
見慣れた景色が自然と目に入る。
児童公園の花壇に咲き誇る秋桜。
犬小屋に繋がれている何時もねむそうな白いグレートピレネーゼ。
塗り直したばかりの横断歩道の白いライン。
廃ガスで煤けた歩道橋。
豆腐屋の看板。
代わり映えのない、朝の街。
そして、違法駐車のバンの陰に潜む、一塊の澱んだ気配。
見張り役の『九蛇卵』。
これで三人目。五日前にも感じた。
ふと千華音は思う。
また人数が増えている。
誕生日―――『奉天魂』が近いせいかしら?
別に、どうということもないのだけれど。『九頭蛇』ならいざ知らず、ただの煩わしい羽虫のようなものだ。
この市営住宅を抜け、角を右に曲がる。
白亜の校舎が見えてくる。
我が学舎だ。
そして、千華音の教室。
夏の日ざしの名残で色あせた時間割と、
プリクラだらけのスチールのロッカー。
黒板の右隅には日直の文字。
千華音は窓際の後ろから二番目の席に腰を下ろす。
周りを包むのは制服を着た小鳥たちの囀り。
メールにスイーツにテレビにうわさ話。
メイクとアクセサリーに彩られた鮮やかな小鳥たちの、朝の唄。
千華音が身に纏った凛とした空気―――『近寄りがたい美人の優等生』のそれ―――に気圧されてしまうのか、誰かが話しかけてくることもあまり無いけれど。
所詮は仮初めの宿、偽りの場。
でも、今ではほんの少し愛着を感じている。
人間観察の役にも立ったし、女子高生気分を知識だけでなく、文字通り肌で理解できた。
何より媛子と話題を分け合うことができた。
始めは車の騒音よりも苛立ったクラスメートたちの囀りだったのに。
今は少なくとも耳障りな雑音ではない。
重くて、大事で、運命の故郷、杜束島よりもよほど好ましく思える。
始業のチャイムが鳴る。
女教師が来る。
小鳥たちの朝の唄はこれで終わり、授業が始まる。
シャープペンシルがノートの上をリズミカルに滑り、踊り、奔る。
ただの情報、そして知識。
数式や元素記号、短歌や年号。
整理され、ピシピシと頭に入ってくる。
意味は何一つ感じないけれど、『知る』ことという行為自体は、千華音の好きなモノの一つだ。
知識の蓄積は、千華音の世界を広げてくれる。
千華音はふと思う。
媛子はどうだったかしら?
そう言えば、夜の喫茶店で宿題を手伝ってあげた事があったわ。
同じ所を何度も質問してきて。
最後には媛子が眠ってしまって、コートをかけてあげたっけ。
などと考えているうちに、いつの間にか授業は終わっている。
そして昼食。
今日も手作りの弁当と飲み物。
チキンサンドと夕食の残りを混ぜ込んだオムレツ、あり合わせのグリーンサラダ。
水筒にはたっぷりのアイスティ。
手間も時間もかかるし、購買部か学食で軽くすませたいところではあるけれど、今は無駄遣いは禁物だ。
ここは裏庭に建つ楡の木陰。
完全に一人きりになれる静寂の特等席。
千華音が学校で一番好きな場所だ。
でも―――。
ふと千華音は思う。
例えばお喋りや笑顔があれば、きっと今よりも何倍も好きになれるのだろう。
もっとも千華音がそう望む相手はたった一人しかいないのだが。
騒がしい放課後。
下校のチャイムが鳴り響く。
校庭を歩きながら、視界の片隅に入ってきたトラックにふっと意識を向ける千華音。
陸上部らしき女生徒たちが、短距離走の練習に勤しんでいる。
速そうなのはあの右から二番目のポニーテルの娘だ。
身体も締まっているし、腕の振りもいい。
何より目に力がある。
もう少し膝のバネを生かせば、もっとタイムは縮まると思う。
例えば、私が走るなら―――。
私が走る?
小さな驚きが、千華音を思索の世界から引き戻す。
そんなことがあるはずがない。
クラブ活動など『御神娘』の自分には無縁の事だ。
身体能力において遙かに劣る同世代の少女になど、鍛錬の相手にすらならない。
付き合うだけ時間の無駄なのに。
なのに何故こんなことを考えてしまったのだろう?
風を切って走る千華音。
耳元で唸る風。
誰よりも速くテープを切る。
見守る生徒たちの大歓声。
その中に、懸命に手を振る媛子が―――弾けるような笑顔が見える。
私は手をあげて応える。
たった一人の相手に。
そのためだけに走ったのだから。
全ては夢想だ
ふふ。
下らないわ。
心地よい風に吹かれながら千華音は歩を早めていく。
パン! とスタートの合図が鳴り響く。
千華音は夜の喫茶店でウェイトレスの制服に身を包んでいる。
黒と白の落ち着いた色調とそれでいてボディラインをさりげなく強調するセクシーな制服。
時間と時給を最優先したつもりだったけど、可愛いと評判の制服を選んでしまった気もする。
これを見たら媛子はなんて言ってくれるかな?
スタイルがいいと何着ても似合う……とか?
ああ、またこんなことを考えている
そう思ってしまう自分が、とても気恥ずかしい。
ざわり。
千華音の五感が『気配』を感じ取る。
店の向かいの通りにあるテナントビルの屋上、その室外機の陰。
また『九卵蛇』の目が光っている。
でもそれだけのこと。
勝手に好きなだけ見ればいい。
気付けば、バイト先の同僚の一人が接客に勤しんでいる。
歳は同じくらい……ひょっとしたら年上かも知れない。
千華音よりも二ヶ月ほど先輩の筈なのだが、その笑顔はまだまだぎこちない感じだ。
何かと千華音の目にとまってしまう。
何が気になるのだろう?
別に媛子に似てなどはいない。
髪の色も、瞳の輝きも、声も、全然違う。
なのに何故、媛子を思い出すのだろう?
強いて言うなら、背が低いことと、舌足らずな話し方と……あと色々と不器用な所くらいのものだけれど。
別なバイト先にだって同じような年頃の娘は何人もいる。
本当に何故なのだろう?
だからここを選んだのか?
それとも、やっぱり何処かに媛子を感じているということなのか?
そんな時、研ぎ澄まされた千華音の五感が『異変』を感じ取る。
皿を下げようとした同僚の一人が、躓いて体勢を崩したのだ。
考えるより先に、千華音の身体は動いていた。
その身を翻し、宙に舞う容器を器用にキャッチすると同時に、同僚の身体を柔らかく受け止める。

何事が起こったのか? と眼を丸くする男性客に向かって千華音が笑顔を向ける
「お騒がせして申し訳ございません」
「……あ、はあ」
男性客はただ頷いている。
そして、千華音は呆然としている同僚を立たせてやる。
「大丈夫?」
その囁きに、やっと我に返った同僚が頷く。
よかった。大丈夫なようだ。
「気を付けてね」
同僚は慌てて仕事に戻っていく。
優雅に踵を返しながら、千華音は新鮮な驚きを覚えていた。
人助け。
『御神娘』の私が。
あまり賢いやり方ではない。
『九蛇卵』に不信感を抱かせるような隙は見せなかったと思うけど、第三者の注目を浴びることは可能な限り避ける……それ大蛇神仕えるものの掟だ。
実につまらない行為だ。
千華音の理性はそう告げている筈なのに。
ならば何故、心の何処かが軽くなっているような気がするのだろう。
この爽やかな満足感は一体何なのだろう?
その正体は千華音には判らない。
でも―――。
媛子が今この場にいたらこうするんじゃないか……そうは思った。
もっともあの子なら一緒になって転んでしまうかも知れない。
そうなったら二人とも助けてあげないと。
思わずゆるめたくなる口元を引き締め、千華音は振り返る。
「いらっしゃいませ。何名様でございますか?」
シフト交替の時間だ。
千華音は急ぎ足で控え室に引き上げる。
急がないと。
すぐに次のバイトが待っている。
ロッカーの扉を開くと、何かが
チョコンと置かれた小さな洋菓子の包み。
店のカウンターでも売っている品だ。
不可思議な驚きと共に千華音は見つめる。
なんなのかしら? これ?
千華音は瞬く間に答えにたどり着く。
ああ、あの娘ね。
お礼?なのかしら。
直接言え無かったから、こんな子供みたいな形で―――。
千華音の脳裏にふとある光景が浮かぶ。
一人、千華音のロッカーの前に立っている
同僚。
耳まで真っ赤にしながら、扉を開けようか開けまいか迷っている。
やっぱり似ている。
こんな所もきっと―――。
そう思って千華音はクスリと微笑んだ。
そして夜は更け、
千華音は家路に付く。
明かりの途絶えた住宅街、もう十二時近い。
結局今夜はバイトを三軒も梯子した。
鍛えてある肉体はともかく、接客業は思った以上に心が疲れてしまう。
シャワーではなくお風呂に入ろう。
浴槽にたっぷりと熱いお湯を張って。
もう一度をアロマを焚いて。
風呂上がりには媛子特製のハーブティを一杯。
それから―――。
千華音は夜空を見上げる。
雲一つ無い夜空には月が見える。
ああ―――。
中秋の名月だ。
おやすみなさいね。
と千華音は心に呟く。
天の月にではなく、地上で眠る人に。
(七)
そこに刻はなかった。
そこでは何も流れず、動かず、変わらず。道徳も、理も、法も、人とそれ以外のあらゆる法則―――『大蛇神』の御名を除けば―――とは無縁の世界。
澱み濁った暗がり、夜闇よりもなお深い漆黒―――神前の間で。
ただ一本の百目蝋燭の炎だけが、彼らを照らしていた。
日本髪の童女、霊句子と、傍らに控える蛇面の女神祇官。
その前では九頭蛇たちが恭しく控えている。
傍らに控えた女神祇官の耳元で、霊句子が声にならぬ声で何事かを呟く。
女神祇官が口を開く。
「『御見留め役』、前へ」
「は」
双磨が前に出る。
「霊句子様曰く。大蛇神様がざわめいておられると。何故か?」
「は」
「この度の『御霊鎮めの儀』は一体どうなっておるのか? 『御神娘』は何をしておるのだ?」
「は」
「毛ほどの狂いでも破滅の基となる……まさか、そのお言葉を忘れたのではあるまいな」
「決してそのようなことは…」
「『御神娘』の言動には何一つ不審な点はございませぬ。確たる証言も、物的証拠もございません。
大雪原の一かけの雪片ほどにも」
「真実か?」
「無論、『大蛇神』に身も心も捧げるべき、『御神娘』が万に一つ、億に一つであろうと大御心に逆らうはずもございません。もしそれがあれば我らが絶対に許しは致しませぬ。断固、正しき道へと引き戻します」
一拍の間をおき、双磨は言葉を紡ぐ。
「ですが」
「何か?」
「兆しを感じます」
「兆し?」
微かにほんの微かに眉を潜める霊句子。
女神祇官の声の鋭さが増していく。
「ようは、お前の勘ということであろう? 御見留め役?」
「……御意」
霊句子が再び、女神祇官の耳元で低く低く囁く。
そのお言葉を受けた女神祇官が立ち上がる。
低く、静かに、唱え始める。
「杜束島の子らよ。『九頭蛇』よ。
『大蛇神』に全てを捧げたる下僕たちよ。
今一度、魂に刻み込むがよい。
ここが何処であるか?
うぬらが何者であるか?
ただ速やかに。
ただ密やかに。
為すべきことを為すべし」
低く静かな、それでいて威厳に満ちた声。
しかし、九頭蛇の面々が雷に撃たれたかの如く、一斉にひれ伏す。
そして澱んだ闇が全てを包み込む。
蠢く泥土の如き、形を持った闇。
その中で何かが……。
音もなく、ひび割れるように―――。
嗤った。
(八)
誕生日まであと半月。
ある晴れた午後、千華音は一通のメールを送った。
書き込んだのはただ一言。
『会いたい』
『何時に』も。『何処で』もない。
ただ『会いたい』と。
それは回答が浮かんだからではなかった。
刻の歯車の軋みに、背中を押されたのか?
悩みの重荷を放り出したくなったのか?
違う。
たぶん、違う。
ならば、どうしてなのか?
認めたくは無いけれど。
もっとシンプルで些細なきっかけだ。
ふと目に止まったのは机の上の洋菓子の包み。
あの日、あの晩、何処か媛子に似たあの同僚の娘がくれたプレゼント。
何となく手を付けられずにいたお礼。
それを見て思ったのだ。
同じなのね。
あの娘と、今の私は。
ロッカーの前でどうしよう? どうしようと? 震えながら戸惑っている。
何処が違うというのか?
気持ちは決まっているのに。
答えはわかっているのに。
馬鹿みたいだわ。
その針先の如き穴から、迷いの堤防が崩れ、押さえ込んでいた想いが溢れ出す。
文字通りの理由。
ただ会いたいのだ。
しかし―――。
千華音の心の奥底に住まうものがある。
芥子粒の一かけより、微粒子よりなお小さな粒がある。
不安という名の微少な帯電を纏った正体不明の粒。
未だ名付けられぬもの。
見えず、聞こえず、名付けられぬ粒。
大蛇神に仕える御神娘が。
死をも恐れぬ筈の戦士が―――。
為す術もなく怯え、震えている。
でも―――。
それでも―――。
初めて千華音から媛子にメールを送ったのだ。
判れば来てくれる。気持ちが通じれば、あの夜のことを許してくれるのなら。
あまりに虫のいい考え……そう自覚しつつもやめることはでき無かった。
言い訳も、謝罪も、全てが虚しく思えるのなら、いっそ運命に委ねてしまおう。
それが千華音の考えた精一杯のけじめなのだ。
でも―――。
必ず来てくれる。そう信じて。
運命が許してくれるなら。
きっと会える。
何処に行こうか。
いつもの駅の待ち合わせ場所?
初めて行った映画館?
あの鄙びたローカル線?
季節はずれの海辺?
それとも―――。
思い出の場所の数々が、千華音の脳裏を駆けめぐる。
何処でも相応しい気もするし、何処でも場違いな気もする。
どうする?
そんな迷いとは裏腹に、千華音の脚は動き続ける。
急がず、もたつかず、あくまでリズミカルに。
脚だけに別の意志か何がが取り憑いたかようだ。
道行く人の姿も、声も、騒音も、吹き抜ける風のように千華音を通り過ぎていく。
その耳に流れ込んでくる軽快なメロディ。
これは? この曲は?
千華音の脚が、ふと止まる。
すぐに曲の出所に気付く。
ああ、ここだったのか。
うん、ここにしよう。
ここがいい。
皇月千華音には、ここが一番相応しい。
ここに、一人佇みながら千華音は思う。
生まれて初めて祈るように思う。
『大蛇神』以外の何かに。
もっと大きく。おおらかな何かに。
媛子はきっと判るはず。
そして、きっと来てくれる。
きっと。
その時、私は―――。
何千人、何万人の中であろうと聞き間違えようのない足音が響く。
紅茶色の髪を風に靡かせ、
大きなリボンを揺らして。
息を切らせて。
その紫水晶色の瞳に、ただ真っ直ぐに千華音だけを映して。

日之宮媛子。
媛子が。
来て―――くれた。
千華音の全身を、魂を喜びが稲妻のように駆けめぐり、弾け、ただ溢れ出す。
来てくれた。
駄目よ。そんなに急いでは。
「媛子」
「あ……!?」
案の定、媛子の足下が縺れ、躓く。
前のめりになった媛子の身体を、千華音は咄嗟に抱き留める。
「あ……」
媛子の頬が羞恥に赤く染まる。
言葉が出ない。
言ってあげたいのに。
溢れかえる喜びに、息苦しいほどに胸がつまって、何一つ出てこないから。
だから、千華音は媛子を抱き締める。
そこは運命の場所。
皇月千華音の、その心が生まれた所。
場末の古びたゲームセンター。
プリクラの前で。
(九)
「行きましょう」
千華音は歩き出す。
媛子がこっくりと頷き、あとを着いてくる。
姉と妹。
先輩と後輩。
心を許しあった親友。
他人から見れば、そんな風に見える光景。
恋人同士なんて、誰も思わないだろう。
「ねえ、媛子」
「な、何? 千華音ちゃん」
「今日は、あたしが予定を決めていいかしら?」
「?」
「いつも、媛子に決めて貰ってばかりいたでしょう? だから今日は私が……?」
「……」
「どうかしら?」
どうするかは考えてある。
緑の中での食事と映画と。
濃密な楽しいデートタイム。
今までの『お付き合い』とさして代わり映えがある訳ではない。
最後の一つ―――を除いて。
でもそれは、媛子からきっかけをもらって動く『お付き合い』の作法ではない。
これは千華音からの媛子への贈り物。
作法じゃない自分を媛子に見てもらおう。
今までは媛子の出す有形無形のサインに、その場で合わせてきた。
でも、それは無しだ。
きっと凄くぎこちなくて、みっともなくて、情けないことになるかも知れない。
でも、それでも良い。
それが本当の皇月千華音なのだから。
誠意と愛情を込めて、自分から、媛子へと。
皇月家からの仕送りは一銭も使わない。
そのためにバイトの時間も増やしたのだ。
お仕着せの格好良さと、見栄えのいい嘘も封印しよう。
これは最初で……きっと最後のデートだもの。
「……」
媛子は応えない。
やっぱり迷惑なのだろうか?
それとも。
媛子は覚えていないと―――言ってくれたけれど、やっぱりあの夜のことが。
どうしても消せない不安が千華音の中で渦を巻く。
気のせいか、媛子の様子がおかしい。
何時でもはにかんで、照れてばかりいる娘だけれど、今日はその度合いがいつもより増しているようにも見える。
その目線が。
その指先が。
その口元が。
ふわふわと所在なさげに彷徨っているようだ。
助け船を出したい衝動がわき起こってくる。
それでも、千華音は媛子の返事を辛抱強く待つ。
焦れない。欲しがらない。
本当の気持ちだから、一瞬でも速く応えを知りたくなる衝動に駆られる。
次々と『回答へと導く台詞』が浮かび、脳裏を駆けめぐる。
お姉様のように。お嬢様のように。
優しく、器用に言えばいい。
でも、それは駄目。
お姉様ぶって、回答を導くことはしない。
真実だけが、欲しいのだ。
それが今日のために千華音の決めた、ルールだ。
でも、この胸の高鳴りはなんなのだろう。
頬に感じる火照りはなんなのだろう。
どうして首筋を汗が流れるのだろう?
いつものリズムとはまるで違う。
鍛錬の汗とも、実戦の汗とも違う、初めての感覚。
本当になんだろう?
震えだしそうなほどに不安なような、逃げ出したくなるほどに恥ずかしいような。叫びだしたくなるほどに待ち遠しいような。押しつぶされそうなほどに胸苦しいような。
こんな、気持ちは?
木の葉が落ちるような、水滴が弾けるような、そんな風に自然に千華音の脳裏に閃いた。
千華音は思う。
ああ、そうだったんだ。
戸惑って、恥じらっているのは媛子だけじゃないんだ。
私だってそう。
お姉様でも、お嬢様でもない。
十五歳の女の子の、皇月千華音だから。
それが今日の私なのね。
私は媛子と同じ所に立っている。
そんな確かな実感がある。
そして―――。
媛子が口を開く。
「……うん」
よかった。
まったく、返事一つでくたくたになってしまう。
こんなにも時間を長く感じたのは生まれて初めてだ。
もし巨人の国の砂時計があるなら、きっとこんな風なものだろう。
大きく、重く、とてもゆっくりと流れ墜ちていく砂粒たち。
なんて幼稚な馬鹿げた妄想だろう。
それでも良い。
それが良い。
本物だから、きちんと重いのだ。
だから一つの返事がこんなも煌めいているのだ。
言葉一つ一つが、とてつもなく眩しく、芳しく、とても嬉しい。
今の千華音は媛子と、同じだから。
「でも……本当にいいのかな? 千華音ちゃん」
「ええ、そうしたいの」
「じゃあ今日は、ぜーんぶ千華音ちゃんにお任せだね」
千華音は、心の底から微笑んだ。
何度目、何十度目かの心からの満足。
これでいい。
たった一度の、
本当の『お付き合い』が始まる。
(十)
そして千華音は媛子の部屋にいた。
媛子のお手製の芳香に包まれながら、千華音は思い返す。
本当に散々な一日だった。
ぶらりと足を運んだ自然公園の散策で、初秋の風を感じながら、千華音と媛子は人造池の畔で歩を進めていた。
夏が還ってきたような強い日射しに、二人とも上着を脱いでしまっている。
剥き出しの素肌に、水面を吹き抜ける秋風が何とも心地いい。
チケットやレストランの席の予約は押さえてはいるけれど、どちらにもまだ少し時間がある。
何処に行こう?
何処だって構わない。
何を話そう?
何を話したっていい。
こうして無為の時を二人でただ過ごすのだって、悪くはないのだから。
何もかもがふわふわとして、それでいて煌めいていて。
何もかもが纏まらない。
思わず媛子のサインが欲しくなる。
どうしようもなく不安で、それでいて心地いい。
闇雲に走り出したいような、ずっと身を委ねて微睡んでいたいような。
快と不安が入り交じり、解け合ったような、
初めての感覚。
ふと千華音の目にあるものが止まる。
軽食と飲み物の屋台だ。
丁度いい。
「少し、暑くない?」
「う……うん。そうだね」
「飲み物を買ってくるわね」
「うん」
そう言うと千華音は人込みを縫って歩を進めていく。
このほんの少しの間が、千華音にはとても心地良い。
ああ、そうなんだな。
千華音は気付く。
結局、私は……。
その時―――。
千華音の耳に飛び込んできたのは。
小さな悲鳴と水音。
媛子が子猫の入ったダンボールを見つけてしまったのだ。
あとあと公園の係員に聞いた説明では、近所の中学生のイタズラだったようだ。
媛子は反射的に、思わず助けようと飛び込んだのだ。
後を追って飛び込んだ千華音に助けられたものの、二人ともどろどろのぐしょぐしょになってしまった。
着替えだ、シャワーだとドタバタしているうちに時は容赦なく過ぎて、決意も、思惑も、予定も、何もかも台無しになってしまったのだ。
こうして千華音はあの日以来の、媛子の部屋に来ているのだ。
媛子は台所でお茶の準備をしている。
西日の差し込む部屋で、千華音は考える。
何一つ予定通りにはいかなかったけれど。
それでも、媛子は微笑んでくれた。
だから後悔はない。
これだって私たちの大切な一日なのだから。
それに、まだ終わってない。
やらなければならないことが、本当に大切なことが、一つが残っている。
千華音の本心。
媛子が好き。
友達としてじゃ無い好き。
女の子のあなたを愛している。
だからあなたを殺せない。
『御神娘』では無い千華音の言葉だ。
畏れと、怯えと、不安と……様々な弱気たちがない交ぜになってこの胸の中で激しく音を立てて渦巻いている。
それは、心を閉じこめ、殺していないから。
でも、後悔はない。
たとえ想いが媛子に通じなくても。
それで良い。
万が一にも―――。
「私も……なんだよ」
そんな夢物語はない。きっと無い。
でも……。
そんなことをふと思うだけで。
いつの間にか千華音の頬がいつの間にか綻んでいる。
我に返った千華音。
私、なんて顔をしているの?
なんて乙女じみたことを。
まったく、一年前の自分とは完全に別人だ。
誰が見たって、きっと呆れ、嗤うだろう。
それでも、千華音は今の自分が嫌いではない。
愚かであったとしても、とても愛おしいと思う。
好きな人と真っ直ぐ向き合い、
嘘偽りの無い言葉をかわして、
そして―――。
媛子。
胸の奥でその名を反芻するだけで、その胸は甘やかな鼓動で満たされていく。
媛子。
でも―――。
幸福で満たされた胸の何処か、在処さえ探れないほどの奥底にある
芥子粒の一かけのような謎の粒。
『棘』とは違う。
『陰』でもない。
これはきっと女の子の不安で。畏れで。
怯え。
あの夜、千華音自身の過ちを思い返すから?
うん。きっとそうだ。
でもいい。
逃げずに、眼をそむけずに向き合ってるから、この大切な『今』がある。
どうしてもっと速く気付かなかったんだろう?
どうしてこんなに決められなかったんだろう?
そうすれば媛子と、もっともっとこんな風に満ち足りた刻を過ごせたかも知れないのに……。
違う―――。
悔やんでも仕方ない。
刻は逆さまには返らない。
十五年間の訓練の刻、皇月家の当主に叩き付けられた言葉。
過ぎゆく一瞬一瞬を、もっと惜しめと。
意味合いは違うけれど
今なら、その意味がわかる。
今なら言える。全てを受け止められる。
たとえその先にあるのが、『奉天魂』のさだめであったとしても。
だから―――。
その時―――。
音もなく、ハンガーが傾き。媛子の上着が床に滑り落ちる。
千華音が立ち上がる
おかしいわね。
風も、揺れも、無かったのに。
部屋の壁掛けが古いせいなのかしら。
戻してあげないと。
ふと、目を向けた千華音の身体が凍り付く。
ポケットからこぼれ落ちてているのは。
媛子の日記帳。
あの日、見ることの無かった日記。
墜ちた衝撃? でもそんなことが……。
一瞬にも満たない刹那の時間、常人では絶対に捉えきれないはずの時。
千華音の鍛え上げられた動体視力が、磨き上げた『御神娘』の感覚が―――。
捉えてしまったのだ。
白いページの中に踊る文字を。
『計画』
『御神娘』
『罠』
鼓動が激しく高鳴る。
今の今まで、千華音の心を満たしていた暖かな充実感。
至福の華が咲き誇る幸福の苑を。
一瞬にして一陣の魔風が消し飛ばす。
何故、文字が見えてしまったのだろう?
何故、読めてしまったのだろう?
自らの瞳をえぐり出してやりたい。
そんな激しい衝動に駆られながら、千華音の手が、日記へと伸びていく。
いけない!!
駄目! 駄目!! 駄目!!
魔風が轟々と吹き荒れる。
それは不安と、畏れと、絶望の唄の合唱。
駄目よ!!
悲鳴にも似た、心の警戒警報(サイレン)が鳴り響く。
全身全霊を込めた、魂の叫びだ。
なのに。
千華音の指が伸びていく。
白魚の如きたおやかな指先が、震えている。
何故、止まれない?
何故。見てしまう?
どうしてこんなことに!?
きっとそれは―――。
偶然という名の運命の仕業だ。
千華音の血と魂に刻まれた運命。
『棘』の名を持つもの。
『陰』と重なるもの。
そして、『粒』と等しきもの。
運命。
その運命が言っている。
空が永遠に空であるように。
月が永遠に月であるように。
万古不変の絶対法則。
お前は『大蛇神』の『御神娘』だ。
いくら耳を塞ごうとも。いくら目を閉じようとも。
逃げることはできない。
絡み付き
千華音は禁断のページを開き始める。
そして、そこには―――。
(十一)
革表紙の小さな日記帳。
右隅にデフォルメされた子犬のイラストが描かれた紙面には、まるまるとした媛子の文字が躍っている。
千華音の目が一心不乱に文字を追い続ける。
理性と本能の歯車が、不気味な軋みを立てて回り続ける。
文字が踊り、情報が舞い、かみ砕かれ、磨り潰され、毒気を含んだ粉塵と刃の破片なって千華音の中にぶち撒かれていく。
粉塵と破片が組み合わされ、切り裂かれた心から流れる血で接着されていく。
出来上がるのは真実という名の残酷なパズル。
これは罠である。
肉体的強者ではない媛子が千華音に勝利するために組まれた密かな謀略だ。
『御神娘』を『一人の少女』とする。
必要なのは徹底的な無抵抗と服従を装うこと。
歓待と甘言、あらゆる手練手管を駆使して精神をじわじわと絡め取る。
使命以外のことに目を向けさせる。
まずは日常的な部分からゆっくりと。
性格を、嗜好を、じっくりと観察、理解していく。
焦ってはならない。
怯えてはならない。
相手は知恵ある恐ろしい獣なのだ。
罠の匂いを感じ取れば、全ては終わってしまう。
蜘蛛の糸の綱渡りだ。
獲物を知り、餌を撒き、おびき寄せ、
そして罠へと突き落とす。
餌は俗世の快楽である。
『食』『飾』『音』『情』。
戦人の性を叩き込まれた『御神娘』であろうと、一皮剥けば『幼子』のようなものだから。
引き回せ、溺れさせろ。
牙を、爪を、嗅覚を、世俗の蜜で、ふやかせ、鈍らせ、削ぎ落としてしまえ。
仕上げは。究極の快楽の淵へと突き落とす。
究極の快楽とは何か?
それは『恋愛』である。
神話時代の勇者も、古今無双の英雄も、逃れられなかった傾国の罠。
『日之宮』の用意した『男』が、『皇月の御神娘』を落とし込み、絡め取る。
候補の選考は進んでいる。
『本土』で育成している『九蛇卵』の男か。
『第三者』に事情を知らせず金で操るか。
どちらも一長一短があり、意見が分かれている。
確かな観察力が鍵となる。
皇月千華音が日之宮媛子に特別な感情を抱いてることに気付く。
友情なのか?
親友であることを超えた想い。
まだ本人もはっきりとは自覚していない萌芽にすぎないが、脈はある。
その方が第三者を介するリスクを回避できる。とても好都合だ。
吐息と睦言の唄を詠え。
肌の温もりを与えろ。
『理想の彼女』の衣を纏え。
見せたいものを見せ、聞かせたいものを聞かせてやるのだ。
優しさの網で容赦なく心を漁(すな)どれ。
千華音を媛子に夢中にさせてしまえ。
そうすれば―――。
千華音の脳裏を容赦なく抉り、穿ち、突き刺さる媛子の文字たち。
『超笑える』
『ほんと、簡単すぎ』
『まるっきり子供。バカみたい』
『笑い出さないようにするのが苦しい』
『超びびった。殺されるかと思った』
『おっきな子猫』
そして、引きちぎられたらしいページの跡。
それはまるで、生々しい疵痕のように見える。
嘘……。
こんなことあるはずがない。
日之宮媛子は。
素直で、真っ直ぐで、愛らしくて。
ぽかぽかと暖かい私のお日様は。
媛子は。
違う。違う。違う。
―――映画館の薄暗がりで掌を重ね合わせた時も。
嘘……。
―――私の肩に小さな頭を預け、子猫のように微睡(まどろ)んだあの日の午後も。
嘘!
―――笑いながらスカートを翻らせたあの波打ち際の一瞬も。
嘘!!
―――千華音の胸に飛び込んできたあの雨の夜も。
あの時も。あの時も。あの時も。
嘘だ!!!
―――二人きりで過ごした時間は……。
嘘だ!!!!
何もかもが……
千華音の心が引き裂かれ、引きちぎられ、苦悶の咆吼を上げる。
虚と空の痛みを超える、地獄の激痛だ。
これが粒の―――運命の正体。
それはとうの昔に判っていた筈の戒め。
目を背け、耳を塞ぎ、言い訳の砂をかけ続けて埋めていたもの。
逃げていない?
嘘だ。大嘘だ。
必死に別の『好ましいもの』に目を逸らし誤魔化し続けていたのだ。
絶対に見たくなかった真実。
気配がする。
日之宮媛子が千華音の背後に立っているのだ。
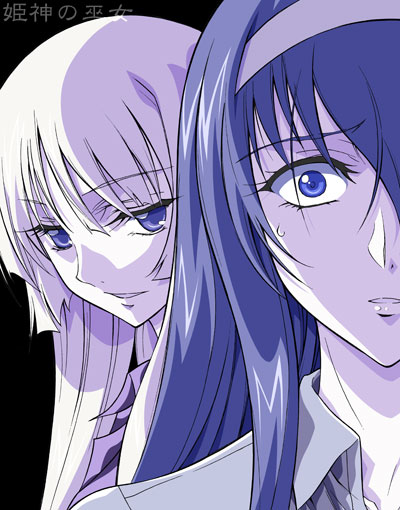
その手には、小太刀が握られている。
その鞘に入れられているのは見まごう事なき『日之宮』の家紋。
ただの一度だって見たことのない媛子の得物だ。
私を、切り刻むための刃。
「見ちゃったんだ」
声が聞こえる。
遠い、とても遠い声。
「ちょっと早い気もするけど、仕方ないね」
そう言って媛子が嗤う。
幼子のように。子犬のように。
一点の曇りもない、無垢の微笑みで。
妖花のように嗤う。
その瞳の輝きは、千華音が一度だって見たことのない光だ。
甘く。暖かく。柔らかく。
密やかにしみ込んでくる。
おぞましくも禍々しい、陽光の微笑み。
「始めよう、御霊鎮めの儀」
「私を殺していいよ、千華音ちゃん」
『御霊鎮め』の日。
二人の十六歳の誕生日まで、あと九日。